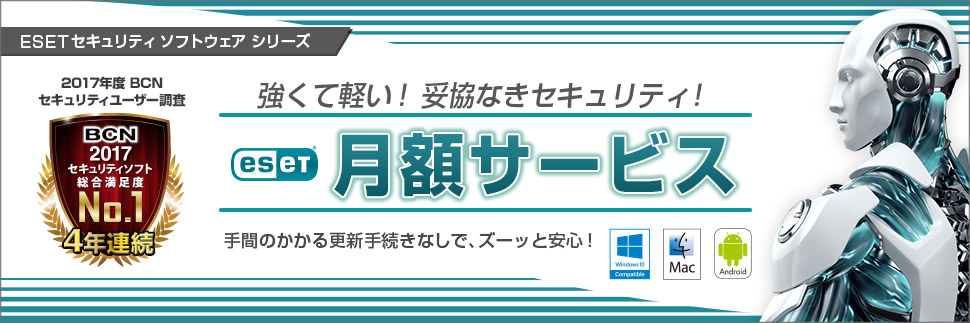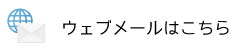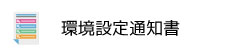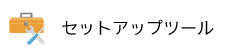先週6日(金)、400年以上続く、秋の伝統の祭典、鹿嶋神社の例大祭が執り行われました。
これに先立ち、前日の5日(木)には、宵祭りの神事が行われ、地域の小学生たちが巫女に扮し浦安の舞を捧げました。
鹿嶋神社の例大祭は、江戸時代初期からおよそ400年以上に渡って、五穀豊穣や地域の平穏を祈り続けられてきた秋の伝統の祭礼です。
祭神として、アマテラスオオミカミとタケミカヅチの神を祀っており、
鹿島立つ神(かしまだつかみ)・鎮守の神として崇敬を受け、
人生の旅立ちや出発の際には、
多くの氏子が参拝に訪れています。
神社の氏子は、本町・田町・六供の本町側と相生町・赤坂・古城・大手の旧藩側からなる、
7つの区で構成されていて、この日行われた宵祭の神事には、本町側と旧藩側の氏子総代や祭神委員らおよそ20人が集まりました。
宵祭りでは、厄病退散を祈る「湯立ての儀」が行われます。鉄釜で沸かした湯に入れた笹を神主が振りまき、氏子の無病息災を祈願しました。
続いて、神主が祝詞を奏上し、氏子総代らが玉串を捧げて、地域の平穏を祈りました。
神事が終わると、厳かな雰囲気の中、本町側の小学6年生8人が巫女扮し、浦安の舞を奉納しました。
子どもたちが踊る、雅やかな伝統の舞に、訪れた保護者や参拝者らは、じっくりと見入っていました。
鹿嶋神社では、この宵祭の翌日の6日に、7区の関係者らが集い、神事が行われ、地域の平穏などが祈願されたということです。かつては、鹿嶋神社の境内で、
秋の例祭にあわせて子どもたちが相撲を取ったという歴史もあるそうです。
地域の人たちに長く親しまれてきた鹿嶋神社の例大祭。これからも長く続けていって欲しいですね。



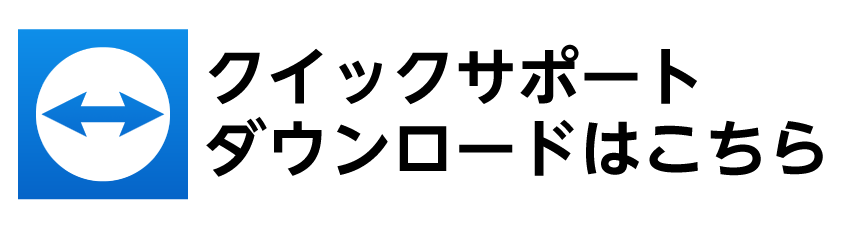
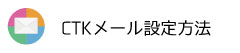
 各地のケーブルテレビ局・民放局などが制作した地域色豊かな番組や、ドキュメンタリー・音楽番組・生活情報などをお届けする総合エンタテイメントチャンネルです。
各地のケーブルテレビ局・民放局などが制作した地域色豊かな番組や、ドキュメンタリー・音楽番組・生活情報などをお届けする総合エンタテイメントチャンネルです。